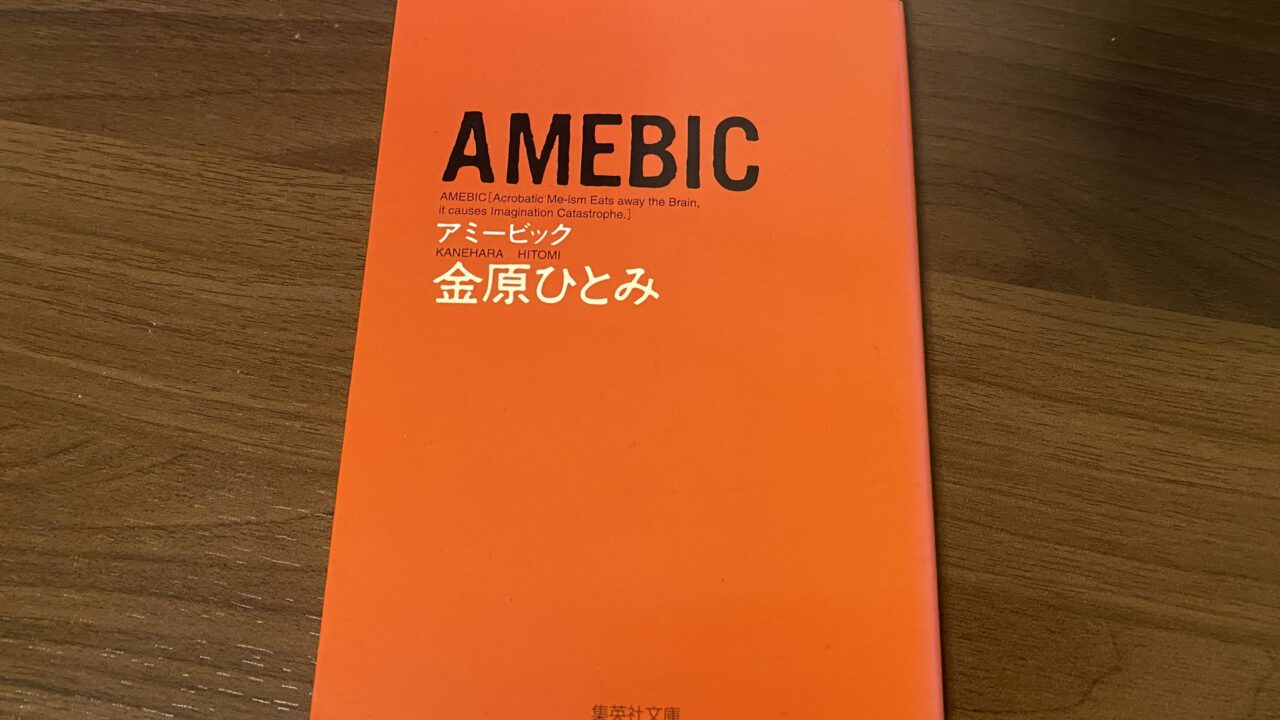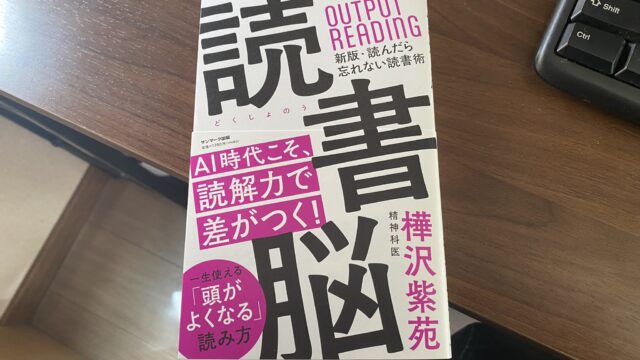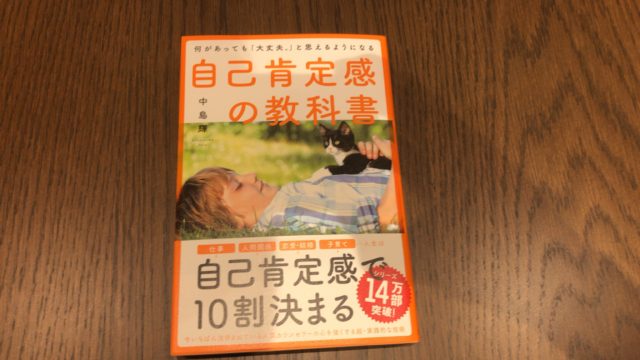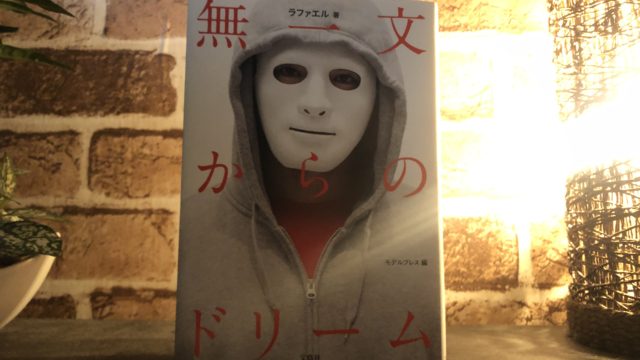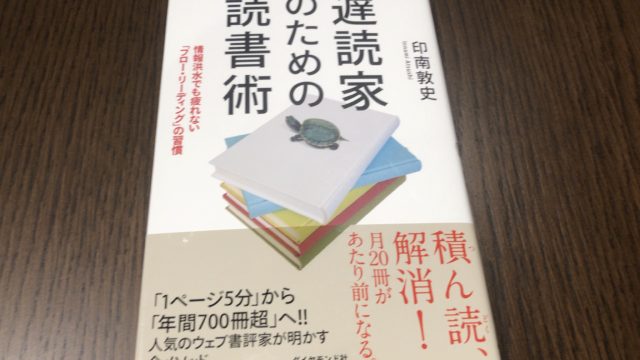YouTubeでも解説しています
こんにちは、TKです。今回ご紹介する本は、金原ひとみさんの『AMEBIC』です。
まずお伝えしたい感想としては、ほとんど理解できなかったなぁという無力感が残ったということですかね。
そもそも本書に明確なテーマがあるのかないのかも、よくわからないです。とはいえ、何かしらの軸とか想いはあるわけですよね。それをうまく感じ取れた感覚は正直ほとんどなくて、悔しい想いをしております。
簡単に概要を言うと、主人公は女性の作家です。この作家は、時折「錯文」を知らぬ間に書いてしまうことで悩んでいます。「錯文」とは、簡単に言えば意味のないめちゃくちゃな文章です。そんな錯分を気づかぬうちに自分が書いており、その錯文を確認しては気味の悪さを感じているということです。
また、極端に痩せており、担当者の男と不倫をしているちょっとヤバい女性なんですね。
また、後ほど語りますが、めちゃくちゃな嫌がらせをするシーンがあってですね、これは笑えました。金原さんが抱いた怒りに対する対抗策が悪意に満ちていてですね、僕はそういう描写が好きで印象に残ります。
ただ、最初にも言いましたが理解するのが難しく、万人にはおすすめできない本ですね。まあ、理解できると思って読むこと自体がそもそもおこがましいのかもしれませんが。
では、本書の全体像や感想などをいろんな視点から淡々と語っていきますね。
自分という存在の曖昧さ
本書の内容を理解しきれなかったとはいえ、なんとなく感じ取れた軸もあります。金原さんは、自分という存在の曖昧さを表現したかったのかな?と思いましたね。本書では支離滅裂な文章(錯文)を書いたり、不倫している男の婚約者の女になりきったりする様子が描かれています。そういった描写から思うのは、誰しもが確固たる存在などではなくて、曖昧な存在なんだというメッセージです。
また、本書のタイトルである『AMEBIC』もですね、この描写と繋がってきます。AMEBICとは、「アメーバ状の」という意味を持つ形容詞です。つまり、誰しもがアメーバのように分裂したりドロドロであったりと、曖昧な存在であることを言いたかったのかもしれません。特にそのイメージを強く感じた文章がありますので、抜粋してご紹介します。
不完全であるという事に、何かが無くなるという事に、私たちは気付かなすぎる。それは確実な、自分自身であるというのに。何かを失っている。何なのか。お前はかつて、後三分の一程の果肉がついていて、六分の一にスライスをされて、今は離ればなれで思い出す事もないだろうが、そう、六分の五があったんだ。そしてそれらが全てあって、初めて君は君自身だったんだ。ライムは灰皿の中で、彼の指でとんと叩かれた煙草から落ちた灰をかぶった。完全であった頃の自分を、ライムは思い出しているだろうか。もっと言えば、君は木にぶら下がっていたはずだ。いや、木と一体だったはずだ。もっと言えば、君が木と一体化していたのなら土とも一体化していたはずだ。君はもしかしたら、地球なのかもしれない。
出典:AMEBIC 162p
バラバラにスライスされたライムは、元々は一つのライムだったわけです。だけど、バラバラになったライム達はそれぞれが完全な個体だと思っているかもしれません。こんなイメージを、金原さんも持っているのではないでしょうか。
金原さん自身も、常に自分は何かを切り離して存在しており、完全な自分の存在など無いと思っているような気がします。他作品での話になりますが、金原さんは消失願望を持っていると明言しています。もう少し正確に言うと、消失している方が自然だと感じているんですね。「金原ひとみ」と認識されている女性は、本当はとても曖昧な存在であり、明確に存在していると認識されていることに強烈な違和感を抱いているのかな?と僕は勝手に解釈しています。
金原さんが抱える感覚を完全には理解できませんが、なぜか複雑な感覚を抱いていることに僕は魅力を感じてしまうんですよね。
笑える嫌がらせ
良い意味で、金原さんの性格の悪さが僕は好きなんですよね。その性格の悪さが存分に発揮されているシーンがありまして、簡単に説明すると、気に食わない店員に領収書の宛名を書かせまくるんですよ。「本屋で本を買って配送を頼もうとしたら配送をしてくれなかったから」という理由でこんなことするんですが、まあ普通に酷いですよね笑。
しかも、宛名をめちゃくちゃ複雑にするところに悪意があって笑えます。例えば「映像研究大学映像研究学部映像研究科経理部」みたいに漢字ばっかの宛名を書かせて、店員をイライラさせる感じです。これ、もちろんフィクションではあるんですけど、本当にこういうことをやりたかった店員がいるんだろうなぁと読んでいて思いました。そもそも金原さんは、生きるために小説を書いています。
普段の鬱憤を小説に落とし込むことで、なんとか生きているようです。金原さんの作品を読んでいると、悪意や怒りが滲み出ている文章を目にすることが度々あるんですけど、そういう文書のほとんどが私怨を晴らすために書かれたものだと僕は勝手に思っています。
そして、そういう文章を目にするたびに、なぜか僕は金原さんが愛おしくなります。直接相手に怒りをぶつけることができないから小説内で暴れ回る陰湿さに、可愛らしさのような感覚を覚えるからでしょうか。
会いたかったはずなのに
金原さんと僕は共通点が少ない人間同士だと思いますが、それゆえに、わかるなぁと共感できた時に大きな喜びというか愛おしさを感じるんですよね。
いや、もしかしたら、共感できたと思いたいだけかもしれませんが。主人公の女は担当者の男と不倫しており、その男のことを好きだと思っています。にも関わらず、なぜか気持ちが乗らない瞬間があるというシーンをご紹介します。
彼と居ると、感情が消える。私は彼と一緒に居ると、感情を持つことが出来なくなる。彼の感情が分からないから、という理由だけではない。彼と居ると、自分の感情というものが分からなくなる。何故この人と会いたかったのか、何を思ってあんなにも求めていたのか、分からなくなる。ただただ私には満たされている感覚だけがある。会えない時間にため込んだ、好き、会いたい、愛している、そういう感覚は消え失せ、ただただ考えているばかりだ。しかしまた、彼が居なくなった途端、好き、会いたい、愛している、そういう感情に支配される。
出典:AMEBIC 87p
この文章を読んで思い直しましたが、共感という言葉は嘘だったかもしれません。わかるような気がすると思いたかっただけで、やはり僕の中にはここまでの感覚は持ち合わせていないような気がします。
もちろん誰しもが、近い感覚は持っているでしょう。例えば旅行前はめっちゃ楽しみだったのに、実際に行ってみたら大して楽しくなかった的な経験は誰でもあると思います。話としてはそういうものに近そうですが、やはり、こうやって話を抽象化・単純化して理解したと思うのは良くないですよね。普通に金原さんに失礼です。僕は好きだと思った人と実際に会えた時、自分の感情が消えるなんてことはありません。
思い描いていた感情と実際の感情に差が出ることはあっても、金原さんほど極端な感覚を抱いたことは無いと思います。あ、ちなみにこのシーンはもちろんフィクション上のものですが、僕は金原さんの素直な想いだと勝手に解釈していますのでご了承ください。
また、この描写も「自分という存在の曖昧さ」を強く表現しているのは間違いないでしょう。人の感情など簡単に移り変わるし、不条理なもの。だけど、その曖昧さを受け入れ切れずにもがいている様子が実に人間味があって愛おしくなります。
さいごに
ここまでいろいろ語ってきましたが、改めて正直なことを言うと、僕はこの『AMEBIC』を理解できたとは思っていません。
最初に言った通り、無力感の方が強く残っています。
でも今は、その無力感自体がこの小説の読後感なんじゃないか、そんなふうにも思っています。『AMEBIC』というタイトルが示すように、この作品は、はっきりした輪郭や答えを提示してくれません。自分という存在も、感情も、欲望も、すべてがアメーバみたいに形を変えながら漂っている。
それを理解させようとも、整理してあげようともしてこない。だから読者の側も、「わかった気になる」ことを許されないんですよね。嫌がらせのシーンも、不倫関係の描写も、錯文というモチーフも、どれも不快だったり、滑稽だったり、よくわからなかったりする。
でもそれらが全部合わさって、「人間って、こんなにも曖昧で矛盾した存在なんだ」という感覚だけが、最後に残った気がします。
正直、読みやすい本ではありません。万人におすすめできる本でもありません。
ただ、自分の感情や存在をきれいな言葉でまとめたくない人、理解できないものを無理に理解しようとしたくない人には、強く引っかかる作品だと思います。
僕自身、この本を好きだと断言できるかと言われると、それもまだわかりません。でも、読み終えたあともずっと頭の中に残り続けている。
それだけで、僕にとっては十分に意味のある読書体験でした。